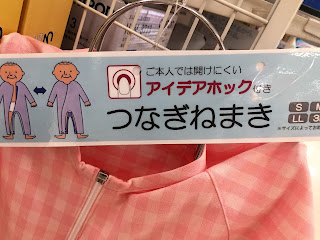相談事業に関する研修。
民生委員児童委員さんや福祉委員さんをメインに
市町社協の担当者のかが対象です。
社協の方はともかく、
ほとんどの受講生さんはプロとはいえない立ち位置の方々です。
で、テーマは何かというと
「対人援助の基本的な部分」です。
日頃、ケアマネジャーさんや介護職員さんに
私がお話ししている内容とほぼ同じです。
(少し噛み砕いてますが)
どうして、ボランタリーな方々に
専門職のとしての基本的なことをお話しするのはなぜか?
それはお互い立場は違っても支援活動の目指すところが同じだからです。
対象者(利用者さん・クライアント)の、その人らしい生活に向けての支援。
自立支援だからです。
その時に、チームを組みたい方々は、
同じことを目指して、情報を共有しないと
云いパフォーマンスはできないですよね。
福祉職の専門性には、
福祉の考え方の啓蒙や、教育(専門職以外の人材育成)もあると思っています。
でないと、地域包括ケアシステムは構築できないでしょう。
福祉学習にも力をもっと注がないと!!!