今日は、
基本的にはオフでした。
朝夕のピースの散歩と夕飯の買い物以外は家におりました。
お昼も、乾麺のお蕎麦で済ませたし。。。
絶対に、本日中に仕上げねばという資料。
某有料老人ホームの職員研修会のもの、、、明後日。
担当さんごめんなさい。
テーマは「グリーフケア」
死別の悲嘆に対するケアのことですが、
在宅にしろ施設にしろ、
ターミナルケアの取り組みが進められています。
介護保険でも加算がついたりして。
しかし、死別後のケアが語られません。
今日、資料を作りながら、
以前、ターミナルケアの研修会でお出会いした
男性の言葉を思い出しました。妻を看取られた方です。
「稲松さん、エンジンってご存知でしょう?!
エンジンはフル回転で動かしているのを急に止めると壊れてしまうんです。
妻のターミナルケアはまさにフル回転でした。
亡くなったとたんに、動かなくなってしまうんです。
まるでエンジンのように壊れてしまった自分が、、、
ほんとに空虚な感じです。
今まで関わったサービスとの関係は切れ
昨日まで妻が寝ていたベッドもありません。
非常に大きな空間が残され。私もいる。」
みたいなことだったと思います。
残された、遺族の方々への支援は
ターミナルケアを推進するならセットのものとして必要です。
その部分へのアプローチなしに看取りのみを推進すると
空虚感を伴った壊れたエンジンのような人たちを作ってしまいます。
いわば救われない不幸せな人たちが新たにできることになります。
どこかの社会保障学者が「介護保険は福祉ではない」とおっしゃってましたが、
公的扶助としての福祉ではなく、対人援助としての視点から見ると
不幸せな人を減らし、幸せな人を増やすのが国の福祉の視点ではないかと思います。
その時に、財源のことだけではなく(もちろん財源の議論は欠かせませんが)
グリーフケアだけでなく、
サービスにつながらないケアマネジャーやSWの相談の仕事も、
目に見えないけれど、対人援助には不可欠の関係性での仕事に対して、
国や国民はもっと目を向けなければならないのではないでしょうか?
と、感じてしまったわけです。(前から思っとるんですけど)
最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。
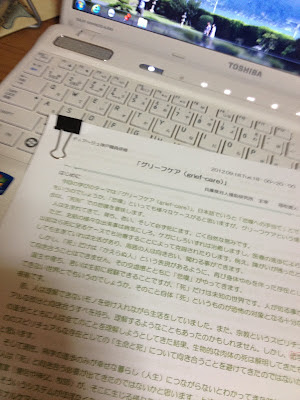
0 件のコメント:
コメントを投稿